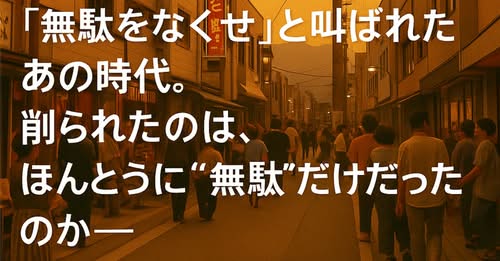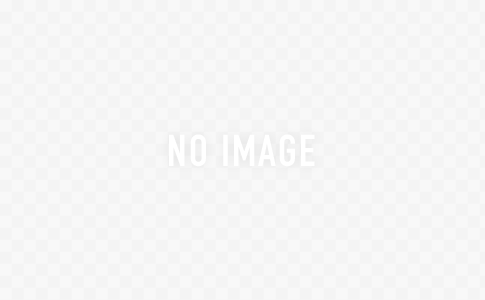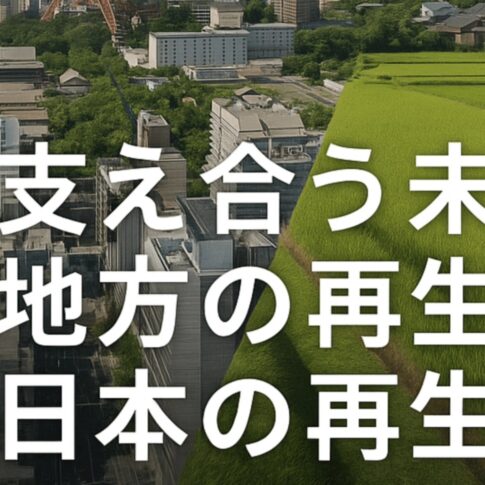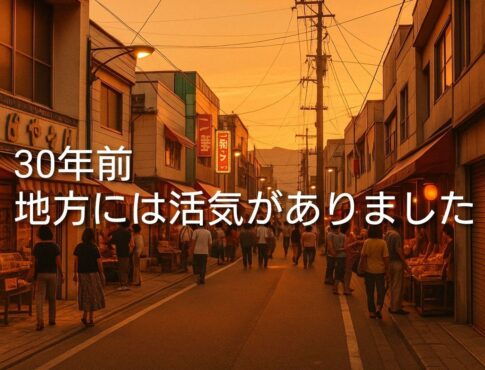【「無駄をなくせ」と叫ばれたあの時代。
本当に“無駄”だけが削られたのでしょうか?】
2000年代以降、
「財政健全化」「行政のスリム化」という言葉のもと、
自治体の職員数は大幅に削減され、補助金も交付税も減らされていきました。
でもその一方で、
自治体に降りてくる制度はどんどん複雑になり、
求められる役割はむしろ増えていきました。
災害対応、危機管理、福祉、教育、包括ケア…
書類、報告、チェック、説明責任…
現場では「できるわけがない」が日常になり、
誰かを責めるでもなく、ただ黙って疲弊していった。
私はそんな姿を、現場で何度も見てきました。
—
三位一体改革の本当の意味。
交付税を削り、「地方分権」の名で
自己責任を押しつけた制度の正体。
でも、制度を設計したのは霞が関。
その責任を負ったのは地方。
そして、制度の中に──地方はいなかった。
「無駄をなくせ」と言われて、
切られたのは“地域の命綱”ではなかったのか。
▼note第3章
第3章|制度から地方が消えていった30年──“無駄をなくせ”のその先で 〜地方が日本の未来をつくる〜|共田たけふみ 長野県議会議員